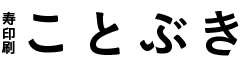津のほん 1986/2 VOL.3より転載
「街の画家」という呼称はすっかり、はやらくなってしまった。そう呼ばれて不愉快な顔をする画家も多いだろうけれど、ぼくは好きな呼び名だ。
パブロ・ピカソが絵の手ほどきを授けたのは父親である〝街の画家”ホセ・ルイスだし、熊本には街の画家〟 海老原喜之助の門下生も多い。福岡では坂本繁二郎、青木繁、尾道は小林和作、岡山には坂田一男というすごい絵描きがいた。彫刻の流政之さんは四国・香川。
数えてゆけば果てもない。
さて、わが津。
ここにあげた、名鑑をごらんになって、「な~んだ、これだけか。あるいは「おっ、案外がんばってるな。」それは、それぞれ感想をお持ちになることと思います。
いずれにしても、これがわが街の芸術文化の人的現状です。
「先生方、ガンバレー」のご支援をたまわりたいものです。
(武)
津の美術界 編集室

三重画廊の主人、山本賢司氏がこんなことを言った。
「芸術をジャンルという言葉でくくってしまったらあきませんに。絵を描く人なら絵を描く人、モノを作る人ならモノを作る人でよろしいやんか」
芸術の世界だけでなく、日本のそこかしこにジャンルや肩書がはびこっている。陶芸家の坪島土平氏によると、それは日本人の特性ということになるらしいが、それにこだわるのは何も普通人に限ったことではない。モノ書きにもその傾向がある。いや、モノ書きこそジャンルや肩書にこだわる。毎日の新聞を見れば、それがよく分かる。
このコーナーも「津の美術界の変遷」とカッコつけてはいるが、結局は「日本画の中の―」 「洋画の中の―」「工芸の中の―」とまず区分してから紹介することになる。その方が便利なのだ。しかし、それは本意ではない。あくまで作品が中心であり、読者の皆さんにも、そのへんを理解していただいて、この人は△△△に優れたものを生み出した人なんだな―ぐらいのことで捉えてほしいと思う。
さて、本題に入る。まずは日本画の津的状況。 他市に比ベ津は南画が強いといわれている。これは奥田竹石、草深香畦ら先達の努力に負うところが大きいわけだが、それだけでない。 藤堂藩以来の市民性、さらには両氏の流れを受け継いだ門人らの尽力も忘れてはならない。
その一人が日本南画院理事の村田清風氏。奥田竹石氏の流れをくみ、最近では色を使った新しい技法も編み出している。しかし、村田氏は墨にこだわり、心にこだわる。やはり南画の持つ〝写意的”な部分に魅力を感じるのであろう。
この村田氏に好対照なのが橋本綵可氏。美術界で日本画といえば、塗り込みなのだが、橋本氏はその塗り込みの第一人者である。京都で宇田荻邨氏に学び、日展にも十三回入選している。この人の足跡をたどると、日本画界の流れがみえてくる。
日本画はどこのジャンルより日展の影響力が強いといわれる。その日展は塗り込み一辺倒。南画は門前払いといっても過言ではない。さらには大家の力関係がものをいう世界で、新参者が入る余地がなかなかないという。戦後、その大家らは東京に集中、現在では流れが京都から東京へと完全に移ってしまった。京都系にとっては残念なことであるが、これもやはり時代の反映か。
ともあれ津の日本画は、塗り込み隆盛の時代にあって根強く南画が残っているといえそうだ。日本の家の中を見渡せば、塗り込みはなくとも掛け軸はある―といわれれば、確かにそうなのだが、一般的に日本画家の多くが日展をめざすという状況の下でみると、やはり特筆すべきことだと思う。それを裏返してみると、案外、津の日本画愛好家は技法の違いや派閥関係などにとらわれず、自由に描いているのではなかろうか。
洋画は、全国的な流れとして多種多様の系列に分かれ、個々にコンクールを開いているのが現状で、津でも旺玄会、白日会、光風会、独立美術協会などの団体に加盟する画家もあれば、一匹狼的なフリーの画家もいる。しかし、画家一人一人には、強烈なセクショナリズムは感じられない。それぞれが自由に作家活動を行っているという感じだ。
それぞれの画家をみていくと、森谷重夫氏は白日会で日展会友。芸大では藤島武二教室に学び、帰郷後、日展に入選。駒田治夫氏も白日会。津高時代は林義明氏に学び、現役で二紀展に入選、多摩美へと進んだ。ほかに北九州絵画ビエンナーレ大賞を受賞した一陽会の土嶋敏男氏や伊藤長重氏、光風会の小野雅生氏、福谷光麿氏、柳瀬たか子氏、一水会の長曽根八郎氏、二紀会の野口節夫氏などの画家がいる。
若手では、独立美術協会の伊藤清和氏、大浦峰郎氏、行動美術の川口清和氏や倉岡雅氏、月輪清氏らの躍進も目立つ。ただ、残念なのは在野画家の大御所が相次いで亡くなったことだ。その代表的なのが平井憲迪氏、そして昨年春逝去された岡本治男氏。平井氏は三雲村出身。長年、高田中学、高田高校で教鞭をとり、教え子が数多く美術界へ進んでいる。岡本氏は抽象画家の第一人者で、モダンアートにも所属していたが、後年はフリーで活躍、一生一画家として押し通した。
美術工芸であるが、焼き物、竹細工、漆に傑出した人物が多い。その中で焼き物はやはり阿漕と広永である。阿漕焼は、紆余曲折はあるが、百三十年という伝統に培われ、現在の福森阿漕に落ち着く。そして、初代福森円二氏の次男守比古氏が陶芸作家として小森窯を開くなど、阿漕焼とは別の新しい道を歩み出している。
広永は川喜田半泥子翁(元百五銀行頭取)の流れが坪島土平氏(大阪出身)へと脈々と受け継がれ、「使われる中に美がある焼き物」を作り続けている。ほかに三重大教授の高田直彦氏(東京出身・芸大)と濱田稔氏。高田氏は、自ら言うように練上で名前が売れた学者肌の陶芸家であるが、やはり「使われる中に美がある焼き物」をモットーにしている。
竹細工では水谷六六斎氏。昨年は伝統的工芸品産業振興会の産業功労者に選ばれたほか、東海テレビ文化賞も受賞した。同氏は京都で修行、七十九才になる現在も独創的で芸術性豊かな籠づくりに励んでいる。漆では、伝統の阿漕塗から脱皮した新経太郎氏。戦前戦後を通して斬新な作品を出し続けた。阿漕塗は先代亀治郎氏で終わり、経太郎氏の漆芸も同氏が高齢(八十才)のため消えようとしている。しかし、次男善夫氏がその跡を継ぐということだ。
新氏の関係で付け加えるならば、長男晴明氏の芸術的センスには卓抜としたものがある。抽象画家として、デザイナーとして常に第一線で活躍してきた晴明氏、残念ながら表面立つことが嫌いらしく、話は伺えなかったが、その作品を見たり聞いたりする限りズバ抜けているように思える。
そのほか種々の分野で作家活動を続ける”わが街の芸術家”は多い。その中には「津は都会的でやりやすい」という人もいる。なるほど、分け隔てなく、芸術に打ち込める土壌があり、その中で切磋琢磨する姿はいかにも県都・津らしく、県内の他都市には見受けられない傾向だ。
しかし、一言付け加えるならば、それが芸術である以上は、先人をどんどん乗り越えていくパワーが欲しい。 先人といっても津の住人とは限らない。全国レベルで活躍する津出身者も数多くいる。そういった人をも含めて乗り越えていくパワーが欲しい。そのためにはやはり芸術の基本にもどって、ジャンルや肩書を越えた、深い感動を呼び起こす作品を作り続けること以外にないような気がする。まさに、山本氏のいう「芸術をジャンルという言葉でくくってしまったらあきませんに」になるのだが……
特集の続きや、津のほんのバックナンバーは弊社にてご覧いただけます。