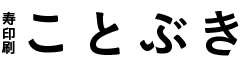津のほん 1984/10 VOL.2より転載
内海康子 (「あの津っ子の会」代表)
1「語り」の持つすばらしさ
「三船神社を はや さしこえて
音に名高い しし岩の
くら骨坂や かはず石
早やと着きたり 犬塚に
下なる川にて 牛水を つかい
お地蔵菩薩と いうて拝む
ヒュー ヒュー ドン ドン
ヒュー ドン ドン」
これは、平木に存在する谷川ふじさんの唄う地蔵踊り唄である。この唄を聞いたのは四年程前であるから、あの時七十八才と言っていたふじさんは、今年八十二才になっておみえである。筋まわしをお伝えできないのが残念であるし、また、聞き書きでもあるから、私がふじさんの唄う意味をしっかりよみとれたかどうか疑わしい。だが、彼女は、話をした後でこの唄をおおらかに、いかにも楽しげに、日焼けした頬を紅潮させ、はりのある良い声で唄ってくれた。その柔和で素朴な丸顔の、生き生きした表情が、肩に背負うた小籠や、かすりもんぺとともにあざやかに記憶されていて、今も忘れられない。
この唄、例の犬塚にまつわるものである。当時、老人会が月の二十四日に地蔵まつりをするということだったから、おそらく今年も行われているにちがいない。それに、この地蔵は、はしかの守り神でもあるそうで、子どもがはしかにかかると、堂の中の石を二つ借りて帰る。すると不思議に治るのだそうである。治ると石を四つにして返す。 それで、小さな堂の内部には小石が沢山積まれてあった。医学のすすんだ現代においてもはしかは、子どもにとって、一度はくぐらねばならぬ関門とでもいえる苦しみであり、事実、私もはしかで盲目になったり、高熱の後遺症で知能障害をうけた例をいくつか耳にしている。すこやかに育てと願う親の心は今も昔もかわりない。峠にたてられた地蔵堂の石を借るために足を急がせる。
はしかの子を持つ若い母や孫を持つ老母の姿を想像する時、幾世を経て伝えられるこの堂に封じられた人の心を感じとることができるのである。この堂の片側にちいさな石の像がある。かつて、一人の猟師が、自分を助けてくれた犬の胴を埋めたところである。ふじさんの語ってくれた内容を素材にして書いてみた犬塚の話というのは次のようなものである。
むかし、平木に住んでいた猟師の天野りょうごは、もろうた荒くれ犬を大事に大事にそだてたそうな。 (中略)
ある日、りょうごは、山のいちばん深い谷へ入って行こうとした。ところが犬がほえる、鳴くばかりで、まるでえものをとりに走り出す気配がない。
「えい、やかましい。そんなになくとえものが逃げるわ。」
それでも、犬は、鳴くのをやめん。 りょうごは、少しずつ腹が立ってきた。
「うるさい!。おれの猟のじゃまする気か。また、前みたように、荒くれてしもうたか、帰ったら、おりに入れてしまうぞ」
とおどした。ところが、いっそう犬はほえたてる。ほえるばっかやない、りょうごの足首にまでかみつく。もう谷へなぞは下りていくなといわんばっかじゃった。それで、なおのこと、りょうごは腹をたてた。
「朝から猟がなかった。これこそはじめてのえもの。そいつを……。えい。いまいましい。せっかく、ここへ来といて、かせぎなしにかえるわけにいかん。おまえがじゃまするようなら、おまえを切るぞ。のけい!。」
腰の刀をふりあげると、エイッとふりおろした。
すると、犬の首と胴が、まっぷたつにわれた。そして、首だけが、キリキリッと宙を三べんまわって、谷底へ落ちてしもうた。それには目もくれず、りょうごは、谷へえものを追うておりていった。
何ということじゃ。 犬の首が谷におったどえらい大蛇の首っ玉にくらいついとるやないか。その両方の首の形相いうたら、もう目をかあっとむいてのう。
りょうごは、はっとした。
「おお、おまえがほえたんは、この大蛇のおるのをわしに教えてくれとったでか。わしを守ろうとしてのう。ものいわんやつや思うて、切ってしもうた。はやまった。あ、あさはかやった。」
りょうごはこの大蛇にひとのみにされる自分を思うて、ぞっとした。そして、まだしっかりと蛇にかみついてはなれん犬の首をガギリッと取りはずすと胴体といっしょに抱いて持ち帰った。(後略)
この犬の胴を埋めたところがこの犬塚だといわれるが、ここで私は、民話の特殊性を探ろうというのではない。これに類する話は、恐らくこの地に限らず山深い各地にあるのではあるまいか。その各地に生きて語る谷川ふじさんに共通する生き生きした人間エネルギーが、民話の底には息づいているということなのである。現代の洗練されたうつくしい世界が好まれる中で民話が好まれるというのはこの人間エネルギーの存在なのである。魂をゆさぶるものの存在が現代では求められている。現代とは云わずいつの代においてもそうなのだとはいえまいか。マスコミに慣らされた現代人の情報過多生活の中ではことに、荒々しい原始の素朴さや、エネルギーが薄れつつあることを自然のうちに我々は感じとり、その人間エネルギーを求め人間性回復の道を探しているのである。
2 民話の底に流れる悲しみへの共感
安古木の双紙によれば贄崎、阿漕浦の海岸は、神宮の御厨であり魚を贄として神前に治める土地であるとされている。網をひいてはならぬ、この浦の魚食うてはならぬとされる海に止むなく網を入れてしまった平治の、網を打つ瞬間の思いは何であったのだろう。日頃より、つい足をのばせば得られる魚を、遠い地に赴かねば得られぬうらめしさ、もどかしさ。ましてや、病人の母を抱える身であってみれば、魚のおどる海へ男の足は向く。禁を犯す人間が果たして弱いのか、強いのか。今の世に愛される人は、大体、人間のために何らかのいさぎよい行為をなすことによって罰せられ、死に追いやられた人をさすことが多い。民衆の声なき声の代弁者、彼は人の心と心に響き渡って密かに語りつがれる英雄なのだ。人のためにつくして罰せられるというキリストの受難に似た民衆の苦難の身代わり者。平治もまた、一帯に住む漁夫の願いの実行者であったから、同情だけに終わらぬ語り草になっているのであろうか。
平治については、安濃の長源寺に次のような話が残されている。長源寺は、今はさびれてしまっているが、古くは伽藍を連ねた立派な寺であった。この寺が、「伊勢や日向の物語り」といわれる所以については、この前書いたのでここでは、伊勢参宮途中の修行者がこの寺で昼寝した際、同じ堂内で昼寝していた安濃村の農夫と魂が入れ替わるが、観音の霊験によって二人の魂は元通りになるという不思議なできごとがあって以来別名を「二つ身堂」と呼ばれたのであるという程度に省略したい。話というのは、この寺の境内に植えられている嫗桜(うばざくら)に関してである。民話風に書きかえると、次のようになろうか。

いよいよ平治の処刑の日が近づいた。盆の十六日、村の盆踊り太鼓がドーン、ドーン鳴っておったがそれも悲しげに聞こえた。さて、平治の家は、長源寺という安濃の寺のすぐ隣りじゃったそうな。
「なあ、平治さんのおしおき、今日じゃったのう。」
「す巻きにされて海へざんぼり投げこまれるんだとよ。」
「こんなむごいやり方ないやないか。」
「だいたい、あの浜へ網打てんいうことが、どだいむちゃなこっちゃ。海はみんなのもんやないか。」
「おい、おい、そんな大きな声出していうてええのかい。」
はっと、口をつむんで、前後に他人のおらんのを確かめると、
「あんなに広い海、土地の者が漁ができんなんてひどいと思わんか。わしらだって、病気の親がおりゃあ食わせてぇもんなあ。」
と、ひとしきり平治への同情が集まる。平治の家ではひっそりと病気の母が歌っておったが、平治が連れ去られたあとは、近所の者がせいのつくものを交替で持って来ては食べさせておった。
「おい、もうぢき暮れ六つじゃ。」
その時、急に激しい雷鳴、黒雲、ザザザー激しい雨。
(こんな激しい雨やったら、きっと苦しむ暇ないやろ。同じ死ぬんなら、苦しまんと一息に死なせたい。)
口にださん村人も一人一人胸のうちで平治をおもうた。こみあげる思いをぶつけるところもない。太鼓の音が大きいのも、そんな心をぶつけたかったのかもしれぬ。平治のおんばがその時、おもわず近くの長源寺の観音堂の縁側にしがみついた。
「せめてのう、極楽浄土へ導いてくだされ。おねがいしますだ。おねがいしますだ!。」
というと、おんばは平治の家にあった桜の木を掘り起こし、どっかと長源寺の境内に植えかえた。
「平治をもし極楽浄土にお導き下さるようなら、この桜、後の世まで咲かせ給え。もしかなえられんだら枯木にさせてたもれ。」
こう願って十七日間の願をかけ、堂にこもって願い祈った。暑い盆のことやった。食べもんは一口も入れなんだ。水だけをのみ、その度に桜にも水をやった。
すると、不思議や、十七日目の夜、夢をみた。 十一面観音様が現れなさって、金色の光を放つ中で、こういわれた。
「そなたの願い、しかと聞いた。平治は無事成仏することであろう。」
というなり消えてしまわれた。おんばは驚き涙にむせんだ。平治の母はそれを聞いて、気がゆるんだかしばらくして息を引きとってしもうたそうな、その後、何年たったかしれぬが、この桜、今もかれずに春になると花をさかせておるぞ。
この「嫗桜」には、平治に対する庶民の温かい目がある。悲しみを共有しようとする思いやりと寛容があるのだ。 平治の行為がどうして特殊な行為といえようか。病気の親や子を持つ者であれば誰しも同じことをするにちがいないという人々の共感である。たまたま、ここにとりあげた平治は安濃の出身となっているが、過去に取り上げられた平治は、ある時上宮寺の壇徒で津興柳山に住む漁夫であったり、真教寺阿古木の記にある村上勘解由之助行春という士であったり、安古木の草紙にある平次盛とかいう伊勢平氏であったり、謡曲では将軍田村麿の家臣であったりで、数はまことに多い。それは津市安濃の地名として古くから津により招かれた土地であるからであろう。古今六帖に阿漕の歌として、
あふ事を阿漕が嶋にひくたいの 度重ならは人知りぬべし
のあるのを知れば延喜以後贄の浦として各種の平治が登場するのも不思議ではない。
私の聞いた先程の嫗桜の話でおもしろかったのは、この十七日の願かけたという嫗(うば)の住んだ家の池にはめかんちのふながるという話であった。片目の魚について柳田国男が「日本の伝説」の中で、全国の片目の魚の存在例が数多くとりあげられてあったが、忠盛塚に関連する「伊勢の平氏はすが目なり」と関連させても、大変に私の興味の呼ぶところである。
3 現代は民話として何を残せるか
民話を大別すると昔話と伝説になろうが、常識的に伝説は土地に密着し著名な人物の行為が中心となって、神社仏閣の霊験談と結びつき、昔話は各地に通ずる要素を持つ。人物が実在すると限らないが、空想をほしいままにしつつその中に人間エネルギーの根源をゆさぶる感動的行為がなくてはならない。それがたとえ人間であっても、動物であっても、それ意外の何物であっても、人間を含む自然界全てを憎むのでなく、優しさと寛容で救い、おおらかに共存し合えるような心の存在が昔話を支えていくものである。そして、何よりも楽しいものでありたい。
現代にあって、我々は何を次の世に語って行けるであろうか。父母と子が食事さえ共にとることができず、まして老人と生活する機会の少ない中で、何を語り継いでゆけるのだろうか。大きな出来事というものは存在する。第二次世界大戦などの悲惨な出来事の中に語れる話はいくらもあろう。また、個性的な人物や奇談奇行の類もあるにはあろう。しかし、人間エネルギーをゆさぶる程の要素となると悲観的にならざるを得ない。
現代の出来事の多くは社会の軋轢の中に死を選ばねばならぬ悲劇である。高度成長し工業化を遂げて行く社会の裏で、犠牲を払っていったものが多い。
自然破壊と村人の移住をよぎなくするダム建設は、現代のおおきな技術革新であり、かんがいと治水に関わる大事業である。三重県内に残る民話の多くは、伊勢平野が米の主産地であり、百姓の生きる場所であるために、それに必要な水の苦しみや水への願いがテーマになっている。 芸濃町の竜王寺(長徳寺) 伝説も、雨乞にまつわる伝説である。この寺、今より凡そ五百年前の開創とかで、第八世大器和尚は高僧であったそうな。禅師が早暁読経する時、毎朝のように一人の美女が現れ、読経が終わると退出する。禅師が怪しんで彼女に詰問すると、この門前の淵に住む蛇体であり、年久しく高僧の出現を望んでいたと語る。そして、
彼女の望む済度を受けさせると、法力によって蛇身を転じた礼に龍鱗と桜種を贈り、旱魃(かんばつ)の際にはこの龍鱗をもって、霊山に就き祈雨すれば必ず降雨あることを約束して去った。以後、錫杖ヶ岳登山し祈雨するのを地元五ヵ村の行事としたという話である。
現在、ダム工事はこの長徳寺の前を流れる安濃川の上流部(芸濃)で進められているが、この寺の前の淵は現在も蛇身の潜むかにみえる美しく、深い淵として昔さながらにみずをたたえている。
同じ地で、水を乞う闘いは古くから現代へ、また未来へと続いて行われているのである。とすると、この上流のダム建設は、現代の民話として私たちが子等に語ってやらねばならないものであろう。それは工事の全貌を語るのではなく、自然破壊の現実や、水底に沈んだ村里の話となることであろう思う。民話の内質は夢物語ではなく、土臭いどろどろの世界であるとも言えよう。創作民話は、そういった素材を、夢をふくらませつつ昇華させ、人間共通の共感と涙とおおらからで答えるものとしてなくてはならないわけである。 炉端で語る老人と子どもの対話の絶たれた現在にあって、私は、かつての老人や父母の「語り」を「書く」形にかえることによって、子どもたちに伝えていきたいと思っているこの頃である。
(津東高校教諭)
特集の続きや、津のほんのバックナンバーは弊社にてご覧いただけます。