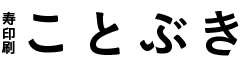津のほん 1985/6 VOL.2より転載
海をボンヤリ眺めたこと、ありますか?
津の子ならとーぜん、ありますよ、ネ。
この、ふるさとの海で遊び、この海の魚や貝を食べてわたしたちは育ってきたわけです。
ところで、近頃、この海があまり、元気でないという噂を耳にしたこと、ありませんか?
津の海の記憶 石原義剛 (海の博物館館長)
足の裏に、でかいハマグリが噛みついた感触が、四十年以上経った今でも残っていて、夏、海水浴にでかけると、新鮮に思い出す。多分、大戦の終わる何年か前の体験だと思う。
西新町の黒板塀に囲まれた母の実家。 横の田圃の溝でアメリカザリガニを取った桜橋通りの姉の家。私より年上の四人兄弟が居て、少々恐れをなして訪れたもう一人の姉の家は阿漕にあった。いずれの家からも、麦藁帽子をかぶせられ、海水パンツ一つで、炒ったソラマメ入りの袋をパンツに結んでもらって、海へ出かけたものだ。
その日はやたらに潮が引いていたのか、小学校へ上がったか上がらぬかの私が、潮が胸まで来る海にたどりつくのに随分と時間がかかったように憶えている。津のどの海岸であったろう。
足の裏が硬いものに当たった。石かと思った。 その石が足を引っぱるように、砂の中へググーともぐり込んだ。私は足を石から離さぬように密着させたまま、とっさに手と顔を水中に突っ込んで石を握った。石ごと海底の砂中へ引き込まれてしまうかと思った。
海面に顔を出して、自分の手からはみだしそうなハマグリを見た。胸は激しく動悸を打っている。そのときやっと自分は泳げなかったことを思い出した。しかし、激しい動悸はそのせいではなかった。生きものと大格闘して獲った喜びであった。今に思うと、たかがハマグリ一つ、小さな手に余ったとはいえ、そのときの感動がどこから発したのか不思議である。
そういえば、私の幼時体験の生々しい記憶はほとんど、動物をつかまえる直前の緊張と、とった瞬間の数秒間にある。トンボ釣りにからまって落下してきたオニヤンマ。岩礁の下からはがしとったトコブシ。サンショの実を煮つめ上流から流したとき、浮きあがってきたナマズ、セミとりはあまり採れすぎてすぐに飽きたものだ。
そんな行動のとき、いつも全く夢中であったと思う。それ以降、ハマグリを獲った記憶がないから、きっとそれらの記憶は成功の少ない部分で、大半の失敗の部分は記憶には残っていないのであろうが、そのころは動物と必死に取っ組み合っていたのにちがいない。
子供の私にとって、海はとてつもなく大きかった。川の流れは深く早かった。空は限りなく広かった。その広大な海、空、川から自在に動く一匹の生きものをこの手に得る試みは至難な技であるとともに、限りなく興味深い、挑戦に値する試みであった。そして得ることは、不可思議で、ありえない偶然でもあった。自然と、海と、子供の時代中、私はそんな風につきあってきた。
親父が志摩半島は和具の出身で、漁師ではなかったが漁業を稼業としていた関係から、連れられて、といっても喜んでついていったのだが、中学校へ入るまでに相当な漁村での暮らしを経験した。したがって、私にとって海は庭であった。そのためか、多くの日本人が、海を恐ろしいもの、近寄り難い場所と感じているのを知ったのは、ずっと後になってであった。
まだ、矢ノ川峠に遮られて、 紀勢線が東西につながらぬ頃に、尾鷲から九木岬をまわて木ノ本へ航く船では、船酔いしなかったのに、帰り道、峠越えのバスにはさんざん酔いで苦しんだ。それから、十数年後、高校生の一人旅で足摺岬へ出かけたとき、夜、大阪港から乗って高知港へ向かった。夏の暑い夜の、満員で足の踏み場もない船底の客室に寝るしかなく、横になった顔へ天井から汗のように吹き出した粘ってい雫が落ちてきても避けるすき間がない。
海は荒れていた。紀伊水道を出ると、船は猛然と揺れだし、客は用意の金だらいにゲロをはきはじめ、次々と感染していった。このとき初めて私は船酔を知った。たまらなくなって這い出した甲板で、また初めて海の恐怖を知った。左右に横倒しになりそうに船が傾くと、漆黒の海の突っ立った波頭を船窓から濡れる灯が照らす。この海に呑まれたら死ぬしかない。それは優しい海ではなかった。
民俗学者の宮本常一氏は、日本人は海を恐れる民であるという。「日本をこのようにして漁民と少数の船乗りたちのほかは海をおそれしめるようにしてしまったのは、寛永十六年(一六三九)のポルトガル船の日本渡航禁止による鎖国のおこなわれたことに起因するのではないかと思う」(「海と日本人」)
江戸二百六十年間、日本人は田畑の上に封じ込められて海を実際に見ることもなく暮らした。海を恐れようにも海を知らぬ民であった。宮本氏のいう漁民と少数の船乗りを除いては。 いま私たちは、世界地図の中に小さな日本列島を見つけて「島国」と呼ぶ。 しかし、鎖国下の日本人にはそんな意識さえなかったであろう。人々は己の住む小さな土地と小さな集団の中に縛られていて、それは彼らにとって全世界であり、その世界から外にはみだすことは許されなかったのだから。多分、江戸時代を通してほぼ二千五百万人の日本人のうち、海の民を含めても、海を文字通り知る人の数は極く限られていたに相違ない。
ごくあたりまえに、日本人が海を見、海に接し、海を知るようになってまだ百年にもならぬ。原始に人間が海からいのちを授かったとはいえ、それは二百万年とも三百万年ともいわれる過去のこと。海を渡って来た日本民俗が列島に住みついてからでも、数千年、数万年を経た。
明治開国で眼前に突然ひろがった海は、もう記憶から消えた異空間であり、恐れなくしては対峙できぬ相手であったろう。坂本竜馬の海援隊もそのはじめは、船酔に悩まされ、へっぴり腰で海へ出て行った。土しか知らぬ大半の日本人はどんな姿で海へ近寄ったのであろうか。

夏になると、津の海岸線に数万人をこえる海水浴の市民が訪れる。この数万人はまだ年々増えつづけている。
「市ではこの海岸を海水浴場として発展させようとして、まず明治三十六年に岩田町の国道から分かれて、紡績会社(現在の県営住宅、津球場のある所) 前を経て、阿漕浦に達する道路を開通した。 大正元年(一九一二)には贄崎新道を開いて市の中心・観音前から贄崎海岸への直通道路を設けた。このころ海水浴客は年々増加しつつあったが、市ではあらゆる機会をとらえて、この両海岸の宣伝につとめた。そして大正四年には市費四百十八円余を投じて両海岸に休憩所と運動器具数種とを建設して浴客の使用に提供した。」
「津市史」は津市での海水浴場のはじまりを右のように記している。
古くから「潮湯治」という海水による治療法のあったことは知られており、明治十三年(一八八〇)兵庫県明石の海岸で、「潮湯治」に西洋式の健康法たる海水浴の考えをとり入れて、兵隊の傷病回復のため海水浴場が開かれて以来、知多や湘南の海岸に次々と海水浴場が設けられて、はじめて漁労や航海とは異なった市民と海のかかわりが始まった。
同じ津市史によると、その海岸線近くに「娼家」が建ち並んでいたとある。娼家と海水浴が如何なる関係にあったか知らぬが、最初期の海水浴には勇気もいったことであろう。とくに女性が、今日の肌もあらわなビキニの水着とは、程遠い海水着であっても、やはり身体の線を衆目にさらす海水浴を真っ先に楽しんだとは思えない。ここにも、長い年月、陸に封じ込められてきた日本人の越えにくい垣根が、海岸に象徴されて残っていた。
それでも、鎖国の時代を通じて、海と陸とを人間のとりもった親密な関係もなかったわけではない。昭和三十七年ごろに途絶えて今はないが、明治・大正まで、津の前浜は秋口から次の夏前まで、大規模小規模それぞれの地曳網漁に賑わったものである。
伊勢湾内は魚介藻にみちあふれていた。 木曽三川をはじめ河川は、太い血管のように、豊富な水に土と森林から吸
い取った栄養分をたっぷりと含ませた上で、心臓たる伊勢湾へ流れ込んでいた。
岸辺近くは、海藻が繁茂群生し、そこに遊び場や保育場、餌を求めて、多種多様の生物が蝟集していた。外洋からさえ、イワシやサワラ、時にはマグロまでが侵入して来た。生命にわきかえる生態系がひろがっていた。
沿岸に住む人にはその藻場に群来する魚をねらって、一網打尽の網を曳いた。記録によると、津の前浜で曳かれた大地曳網には近在から二百人~三百人の曳子が集まってきたという。その網数も十統をこえる。
地曳網の獲った魚は重要な蛋白食糧であったが、また、貴重な肥料でもあった。 地曳網を曳いた人々は漁師であるとともに百姓でもあって、鎖国の時代に陸に完封されながらも海を利用してきた特異な人々であった。そこに、伊勢は津でもつ、伊勢平野の豊饒の真因があったのではないだろうか。
魚ばかりでなく、海藻も、ヒトデさえも肥料として残さず使われていた。それを獲る網の大部分は藁を撚り編んで作った。田圃の多忙な季節には地曳網の魚は少なく、農作業が暇になると魚が来てくれた。彼らはまた、注意深く魚たちが子を産む季節には網を曳かぬように心がけた。

海と陸は環につながっていた。人間がつくりだしたというよりも、人間を部分に組み込んだ造化の環であった。津の土地に住んだ人々が曳いた地曳網の時間は、曳かなくなった時間の数十百倍も長いのであるが、その時間さえもう忘れられてしまう。
いま海では、収穫する土地にかわって、さらに、米や麦にかえて海で海苔を耕す。肥やしは、住民の余り捨てる排泄の水。海と陸の長くつづいてきた環の方向が逆転した。
それでも若者は海へ向かう。しかし、接近の仕方は私の体験とははるかに遠い。ヨット、ウインドサーフィン、ボート、アクアラング。スピードとスリルを海はつくりだす。黙然と網を繕う漁民のかたわらを走る喚声を添えて。
生きものの感触や、生態系や、海と陸の連なりなどと、感傷気味に語っている間に、若者たちはさらりと海への恐怖を捨てさってしまったらしい。海は若者にあふれ、若者で占領される。
鎖国がめぐらした海の壁も、飛行機のひとっ飛びで、 次第に意識から消えていく。若者たちは臆せず、禁じられた”ポルトガル”へ乗り出していく。きっと、この若者たちが海と人間の新しい関係をつくりあげるのであろう。私たちに出来るのは、彼らに私のハマグリ感覚を強要せぬことであろう。彼らに、余計な計画を残したりしないことであろう。
とは頭で考えつつも、やはり足の裏のハマグリの感覚はいつまでも消えぬ海の記憶である。
特集の続きや、津のほんのバックナンバーは弊社にてご覧いただけます。