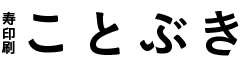津のほん 1984/12 VOL.2より転載
すっかり、冬になりました。
冬の日曜日、どうお過しですか?
このあたりの冬景色、なんとも穏やかで落ちついていてエエもんです。
ヒマならお子さんを連れて(あまり嬉しがりはしませんが…)、もちろん、ひとりでも結構、散歩のつもりでわが街の古寺巡礼はいかがでしょう。
少々ジジむさいとおっしゃるムキもおありでしょうが、少しばかり蘊蓄をポケットに忍ばせて行くと案外、楽しいものです。
老後の予行演習にも役立ちます。
四天王寺 四天王寺に眠る名士五人

「寛政一揆」の茨木理兵衛
茨木理兵衛、本名・重謙は明和四年(一九六七)に津で生まれた。彼は寛政二年(一七九〇)、二十三歳の若さで郡奉行に任ぜられ、藩の農業政策を担当することとなった。郡奉行時代に行った主な事業を紹介すると—
まず、 安濃川上流の雲林院井堰の改修。これにより、同地区の干害が解消された。また、松崎崎新田の開発に着手、寛政四年から三年をかけて、これを完成、六町四反強の新田を安濃川と志登茂川の河口付近に誕生させた。
その一方で、理兵衛は、傾きかけた藩財政の建て直しに躍起となった。そのために、商人や資産家から借り入れしていた藩債の金利を引き上げたり、償還期限を百年延長したりの政策を押し進めたほか、「常回り目付」という代官直属の監視役を新しく置き、農村を見回らせたりした。また、厳しい倹約令を出して、財源の確保にも努めた。
だが、これらの建て直し策は、結果として裏目に出て「寛政一揆」を引き起こすことになる。寛政一揆とは、藩が一志郡西部の山村に、田畑山林を均等に割りつける「地ならし」を実施しようとしたのに対して、農民が反発、騒ぎ出した百姓一揆。この失策で彼自身、それ以後、歴史の表舞台に出ることなくその生涯を終える。
一揆は、寛政八年十二月、一志郡小倭郷(白山町)から火の手が上がり、藩内各地に広まった。藩はこの一揆の首謀者三人を処刑したほか、理兵衛に対しても知行や屋敷を取り上げた。面白いのは、その理兵衛へのおとがめ。
藩庁から理兵衛の屋敷に処分を伝える上司が来た。その上司は平伏する理兵衛に対し、「その方、氏名のうちの『イ』の字一字をお取り上げに相成るぞ」と言った。それを聞いて理兵衛は、ハタと考え込んでしまった。
彼の名は「イハラキ、リヘイ」であるから『イ』の字が二つある。しかも、一番上と一番下に一字ずつある。上の字を取ると、「ハラキ、リヘイ」。切腹せよの意味である。下の『イ』の字を取ると、「イハラキリへ」で何の意味もない。
弱り果てた理兵衛は、「私の名前には上下に『イ』の字が付いております。 よって、上下どちらの『イ』の字をお取り上げになるのかをお示しくだされば、有り難きしあわせ……」と上司に尋ねた。すると、その上司は「たわけたことを申すな! お上は上であり、上を取れーなど言うはずがなかろう。下々の者は下を取るのがならわしであるわい」と言って笑い出した。要するに、切腹申しつけの使者がトンチを使い、理兵衛を助けてしまったのである。
寛政一揆の首謀者とは、多木藤七郎、 町井友之丞、森惣右衛門の三人で、安濃川河原で打首となった。しかし、この一揆の本当の理由は津藩内の新旧官僚の勢力争いであって、余りにも急進的な政策を遂行した人々に対して、農民の不満が爆発したことによる。
ところで、理兵衛の父は、津藩の藩士で俳人の茨木素因(本名・重光)。享保六年(一七二)生まれで、藩内では三百石、騎馬隊長にもなったが、俳人としての方が有名で、大谷町の密蔵院には素因の杖塚がある。理兵衛も俳句を詠んでおり、号を「籬芳」と言った。
写真の元祖・堀江公粛
堀江公粛、本名・鍬次郎は慶応二年(一八六六)、三十五歳の若さで亡くなっている。彼の名は写真にたずさわる人たちによって語り継がれ、「日本の写真の元祖」とも呼ばれる。
そもそも、写真とは天保十二年(一八四一)、長崎の輸入商、上野俊之丞が、薩摩の島津斉彬を撮影(銀板写真法)したことに始まる。その日が六月一日であり、毎年、この日を「写真の日」としている。
さて、堀江鍬次郎であるが、その写真草生期の安政年間、藩から長崎へ舎密学(今の化学)の研究に派遣されている。そこで鍬次郎を教えたのが「ボンベ」という蘭医。彼は当時としては最新のコロヂオン湿板法の写真機を持っていた。鍬次郎はそれに異常な興味を示した。
最新式の写真機を見たのは、鍬次郎のほかにもう一人いた。上野彦馬という人物。彼は俊之丞の息子であるが、父が写真をやっていることは知らなかった。
二人は写真の写し方を覚えようとしたが、肝心のボンベがその使い方を知らなかった。そこで、見よう見まねで暗函を作り、原書を片手に薬品づくりに取りかかった。アルコールを作り、硫酸を作り、青酸カリ、アンモニアを牛の血や骨から抽出したりした。
硝酸銀はメキシコ銀貨をとかして作った。何度となく失敗したが、ようやく、コロヂオン液を作り、ガラスにそれを塗って撮影した。露出は五分だった。定着してみると、やっと僅かに写っていた。
彦馬は、その後、長崎で写真館を開き、名をはせた。鍬次郎は津へ帰り、藩校の「有造館」で化学を講じ、彦馬の「舎密局必携」を校訂し津で出版。また、藩主に新しい写真機を購入してもらい、多くの写真を撮ったというが、彼にとって人生はあまりに短すぎた。
幕末の偉人・斎藤拙堂
斎藤拙堂は、寛政九年(一七九七)、江戸藩邸で生まれ、昌平校に学んだ。二十四歳で「藩校講師加リ」に任ぜられ、津に来た。彼は漢学者として、また、詩文家として有名だが、外国のことにもよく精通し、幾多の著書を残している。さらに、勤皇家として、津坂東陽とともに結城宗広卿の顕彰にも努めている。
彼が最初に刊行したのは「拙堂文話」 (正続全十六巻)。ここで彼は中国、日本の学者、文人の文章を論じた。これを書いたのは三十四歳の時で、これを機に拙堂の名は世間に知れ渡った。
その一方で、「月ヶ瀬紀勝」「救荒事宜」「三倉私義」などの名文も出している。海外の文献では「海外異伝」「海防五策」「魯西亜外記」などがある。また、写真の堀江公粛などを、舎密学の研究に長崎留学させるため援助している。
天保十二年(一八四一)に拙堂は郡奉行となり、幕府の天保改革に呼応して、庄屋の不正を摘発。その後、弘化元年(一八四四)に、藩校・有造館の主任教授である督学(三代目)に就任、 開明的な色々な施策を打ち出した。例えば、洋式大砲の鋳造、壮士隊の編成と操銃訓練などはすべて拙堂の指導による。
彼は慶応元年(一八六五)、六十九歳で亡くなっているが、晩年には比佐豆知神社(鳥居町)あたりに山荘を持ち、そこで学者、文人、門人たちと勉強会を開いたり、時局を論じたりした、という。そこに現在、「拙堂先生山荘跡」の石碑が建っている。
人気力士・荻右衛門
伊勢ヶ浜荻右衛門の供養墓が、ここ四天王寺にある。 荻右衛門は、伊曽島村(今の桑名郡長島町)出身の力士で、江戸時代の寛政年間(一七八九〜一八〇一)に活躍した。三重県では、引退した三重ノ海のほか、大関・琴風、巨砲、北尾などが角界に出ているが、荻右衛門はその先駆者であった。
荻右衛門は、安永四年(一七七五)、十九歳で大阪相撲に入り、「鎌ヶ岳」と称したが、安永七年には江戸相撲に転じ「鳥羽海」と改称した。伊勢ヶ浜と名乗ったのは寛政二年(一七九〇)のことで、寛政五年、東幕内入幕、寛政八年、前頭四枚目を最高位に引退している。
伊勢ヶ浜の名は、この荻右衛門を初代として、五代まで三重県の力士によって襲名されている。また、彼の出身地の伊曽島村からは五人もの力士が出ている。荻右衛門は、「鳥羽海」時代、菰野藩・土方家に三人扶持で召し抱えられている。身長一九七センチ、体重一三七キロというから巨漢であった。
彼は文政四年(一八二一)に亡くなり、墓は故郷の村にある。四天王寺の供養墓は、荻右衛門のファンであった伊勢戸兵蔵が建てたといわれているが、はっきりしたことは分からない。墓は二メートル余りの高さで、そこには「濱翁秀荻居士」と刻まれている。
二日坊主の俳人・菊地宗雨
二日坊は、江戸時代の俳人で、本名を菊池宗雨という。正徳元年(一七一一)、 立町で生まれた。家は「菊池屋」という代々続いた薬屋。しかし、彼は家業よりは一生を俳諧に過ごした人物である。
彼がなぜ、二日坊といわれるようになったのかーそれは彼の生家が薬屋だったのに、その勉強はそっちのけ、いつも書物ばかりを読んでいた。そのため、父親が癇癪を起こし、無理やり京都・大宮の、さるお寺へ弟子入りさせてしまった。
宗雨は渋々、仏門に入ったが、心細くてしょうがない。たちまち望郷の念にかられて、二日目にはその寺を逃げ出し、津に帰ってしまった。これには父親もあきれ、知人たちも「世の中に三日坊主というはあるが、二日でやめてしもた。二日坊主や、二日坊主や」とはやしたてた。
こりゃ面白いーと宗雨はそれ以来、「二日坊」と名乗った。彼はその後、俳人として有名になり、多くの門弟を抱えるようになった。しかし、その後、彼は愛する息子を失い、非常に嘆き悲しみ、天然寺の方丈に頼んで、今度は心底から坊主になってしまい、「二日坊」の号も「帰旧法子」と変えた。
彼の杖塚は、ここ四天王寺山門脇にあり、また、岩田町の阿彌陀寺にも笠塚があった。しかし、笠塚の方は戦災で破壊され、今はない。四天王寺山門の杖塚の右側面には「聞きたいも病むひとつなり時鳥」(病んでしきりに聞きたいのはホトトギスの声だの意)、左には「初雪や頂いて行、踏で行」とある。作風は滑稽、洒脱、極めて町人的なものが多い。
天然寺 ~旧異宗珍居士

隠れキリシタン異聞
ここ浄土宗・天然寺の境内に「旧異宗珍居士 荒木忠左衛門」と書かれた一風変わった戒名の墓が残っている。元禄十三年(一七〇〇) 十二月、肥前国五島藩士とあるところから、キリスト教徒弾圧が厳しかった江戸時代の隠れキリシタンの墓であることが分かる。
この戒名は「クリスチン居士」とも読める。この読み方が分かったのは、つい最近のことで、忠左衛門の孫にあたる長崎市筑後町、団体役員、荒木徳五郎さんからかかってきた問い合わせの電話によってであった。
江戸詰めだった忠左衛門は、肥前に帰国する途中、お伊勢まいりに立ち寄り、津の城下の旅籠で疱瘡(ほうそう)にかかり死亡した。津藩の初代町奉行・玉置甚三郎が遺体を検分したところ、胸に十字架を発見した。当時、名奉行の誉れ高かった甚三郎は、ことの重大さを思い、自ら戒名をつけ、天然寺住職に埋葬と遺品の送り付けを命じて、忠左衛門が隠れキリシタンであることを幕府に知られぬよう処置した。
その後、この秘話は三百年近く、荒木家に受け継がれ、「当主一代のうちに必ず、天然寺を訪ねること」が義務づけられていた、という。墓は天然寺の境内を入って、石畳をたどっていくと、その一番奥のマキの木に囲まれたところにある。子孫の荒木さんらはこの墓を見るたびに「現在わが家があるのは、心温かい津藩士のお蔭」と感謝している、という。
福蔵寺 ~谷川士清

国語辞典の生みの親
五十音順に配列した日本で初の国語辞典をつくった谷川士清は宝永六年(一七〇九)、津の八町で町医を営む谷川義章の長男として生まれた。士清は十三歳の時、家業を継ぐため京都へ医学の勉強にやられ、二十七歳の時、父親の要請で帰郷、町医(産婦人科)を引き継いだ。
しかし、京都時代に医学とともに学んだ国学、神道を捨て切れず、医業のかたわら、日本書紀の注釈書である「日本書紀通証」づくりに励んだ。それが完成したのは二十余年後の宝暦元年(一七五三)であった。また、その後、わが国初の国語辞典 「和訓栞(しおり)」をも完成させたが、これの刊行を見ることなく、安永五年(一七七六)、六十八歳で亡くなった。
士清の死後、谷川家の人々は彼の意志を継いで「和訓栞」の刊行に努力し、 通巻五十三巻、八十二冊を完成させた。しかし、それは家財を投げうつ大事業で、着手してから完成までに何と百十年の歳月を要した。
それほどの実績を残した士清だが、世間一般にはあまり知られていない。その理由の一つは、彼が幕府に対して強い反発を持っていたからであり、幕府も彼の業績が評価されるのを嫌った。さらに、彼の門弟からは多くの反幕論者や倒幕運動家が出ているほか、息子の士逸などは所払いの処分まで受けている。
正覚寺 ~キリシタン墓~

津市内には、もう一つのキリシタンにまつわる話がある。ここ正覚寺(通称・赤門寺)の「香林院自性妙円大童女」と戒名がつけられた墓がそれである。このお墓の存在が分かったのは、藤堂家から朝香ノ宮家に嫁がれた朝香千賀子さんの話からだった。この人は敬虔なクリスチャンとして知られている。
この朝香家をある日、観海流の家元・山田慶介氏が訪れた。その時、千賀子さんは山田氏に、「昔、藤堂家に私と同じようにキリスト教徒であった姫がおられ、 正覚寺というお寺に葬られているはずですから、一度、私に変わって回向をしてあげていただきたいのですが・・・」と代参を依頼した。
藤堂家にキリスト教徒の姫がいた」という話は、市史の上での新発見。それが事実であれば、どのように埋葬したのか、ということも興味深い。そして、これら一連の調査の中で浮かび上がってきたのが、二代目藩主・高次公の息女で、幼名を「お石」とよばれた姫の存在。
しかし、姫が死んだとされる正保元年(一六四四)は、わずかに四歳のころである。たとえ、敬虔な信者であったとしても四歳でキリシタンであったとは考えにくく、その結果として出てきた人物が、この姫の母親だった。
市史研究家たちは推理した。この母親は、武家でキリシタンの古田織部の娘ではないか。彼女も父親と同じくキリシタンだったが、高次の寵愛をうけて側室になった。しかし、幕府の諸藩に対する風圧が強まる中、藩主の身辺に御禁制のキリシタンがいることは不都合。
そんなある日、お石姫が亡くなった。それを機に藩内には、その側室に「キリスト教を改宗させよう」という空気が強まり、信仰を捨てるか、あるいは死かーの選択を迫った。彼女は信仰を捨て切れず自決の道を選んだ。誰よりもこの側室を愛した高次は「最愛の者を藩のために死なせた」と悲しみ、お石姫の死を幕府に対するカムフラージュに手厚い葬儀を行った。
正覚寺には「赤門」があるが、これが何故ここにあるのかーはこれまで謎とされてきた。しかし、この説が事実とすれば、高次公が葬儀を行うにあたって下付したものとも考えられる。また、藤堂家の家紋を正覚寺の紋として使用することも、この時に許されたのかも知れない。
寒松院 ~藤堂家の菩提寺

維新と戦災と寒松院
バイパスを南下すると、阿古木橋の手前左手に大きな五輪塔が、生垣越しに林立しているのが目につく。これが歴代津藩主の墓所となった寒松院である。寺は戦災で焼失し、今もって寂れたままの状態だ。
この寺は、江戸時代には昌泉院といったが、二代藩主・藤堂高次が、藩祖・高虎の霊をまつるようになってから、高虎の院号をとって寒松院というようになった。それ以後、藩主の菩提寺として重きをなし、藩費で維持された。
藩祖の百五十回忌には鐘と鐘楼、十代藩主・高兌の時には本堂、新書院、山門が再建されたりして、その勢いは他に並ぶものがなかった。ところが、明治になって藤堂氏が離檀し、昭和二十年の戦災では全焼してしまった。
南の入口から入ると、正面に本堂がある。しかし、これは戦後、他所から古い堂を持ってきたもので、昔の寒松院をしのぶことができない。左手墓所には、初代・高虎、高虎夫人をはじめ、歴代藩主の壮大な五輪塔が立ち並んでいる。
西側にある六代・高治から十代・高兌の墓は板石塔婆になっている。そのなかで、七代・高朗の墓碑が欠けているのは、昭和二十年六月二十六日の爆撃によるものであり、当時の傷痕がこんなところにも残っている。
浄明院 ~江戸川乱歩
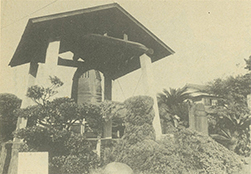
乱歩の先祖は生粋の津人間
怪人二十面相や明智小五郎で知られる推理小説界の大御所・江戸川乱歩の祖先の墓は、ここ浄明院にある。乱歩の本名は「平井太郎」で、この墓碑に刻まれた建立者が乱歩その人である。
乱歩の戒名は「智勝院幻城乱歩居士」。それは浄明院の和尚がつけたものだ、という。乱歩の墓は一時期、ここにあったが、現在は未亡人の住む東京へ移されている。
「私の本籍は三重県津市にあるが、一度も住んだことがない。祖父の代まで藤堂藩の藩士で、津市に住んでいたが、父は郷里を離れて大阪の関西大学を出、しかし、最初の就職は同じ三重県の北部の名賀郡の郡書記で、同郡の名張町(現在は名張市と改称)に二年ほど住んだ。父はそこで津市から母を迎え、明治二十七年に私が生まれた」(「探偵小説四十年」から)
津と乱歩という意味からは、乱歩はあまり津に足跡を残していない。そもそも彼自身は、千石取りだった先祖が藩に召し抱えられるようになったきっかけを心よく思っていなかったらしい。先祖は、二代藩主・高次公に仕えていた於光(四代・高睦の生母)の縁によるものであり、これを乱歩は「武功によってでなく、女の力によって出世した」と率直に述べている。
上宮寺 ~清韓長老

ここ上宮寺に「南禅寺清韓長老墳」と刻んだ高さ六十センチほどの自然石の墓がある。京都・南禅寺といえば、全国でも指折りの名刹である。なぜ、そこの長老が、この津の地で葬られているのか?
時は慶長十九年(一六一四)、南禅寺の清韓に豊臣秀頼から京都・方広寺の大仏殿の梵鐘の銘文を起草してほしいとの依頼があった。 これが世にいう「大仏殿鐘銘事件」の始まりだった。
清韓は銘文に「国家安康 君臣豊楽」を入れた。梵鐘の鋳造はその年の四月から始まり、八月には鐘供養が行われる予定だった。だが、その直前の七月末になって、突如「待った」がかけられた。
「国家安康は家康の名を引き裂き、君臣豊楽は豊臣を君とし・・・などと読める」と家康がクレームをつけたのである。これには清韓も驚いた。豊臣後の天下をねらう家康としては当然の帰結というべきであったが……
清韓は、家康を害する意はなかったと弁明したが、聞き入れられず、銘文の起草者としての責任をとらされ、駿府に送られた。慶長九年(一六〇四)、京都五山の僧侶にとって最高職の南禅寺住持職にいたこの長老は鐘銘事件後、その姿を歴史の表舞台に現さない。
清韓が上宮寺に来たのは、大阪冬の陣、夏の陣が過ぎ、豊臣家が滅んでのちのことである。清韓の生地は奄芸郡三宅(現在の鈴鹿市三宅町)であったが、津に来た理由もやはり、そういった関係からであろうか。上宮寺には、その時、手みやげに持ってきたという秀頼直筆の軸がある。「南無阿彌陀仏」と書かれてあり、秀頼九歳の時のものだ、という。
鐘銘事件については、清韓のほかにもう一人、関わりのある人物が津に来ている。 辻越後守家種である。家種は問題の梵鐘の鋳造者である。その後、津に住みつき、子孫らは観音寺の銅燈籠や専修寺の梵鐘などをつくり、名工としての地位を築いた。
専修寺 ~高松院

津は一身田の高田本山・専修寺の境内には大きな梵鐘がある。この梵鐘は高松院が、不幸な事件で悲憤のうちに亡くなった本山の第十五世御門跡・堯朝上人の菩提を弔うために造ったものである。
高松院は津藩の初代藩主・藤堂高虎の娘で、蒲生忠郷に嫁いだが、忠郷が死亡し、嗣子もなかったため蒲生家を離れ、高虎のもとに帰っていた。そうしたことから、堯朝上人の内室として一身田・高田本山に再嫁した。
ところで、十五世御門跡を襲った不幸な事件というのは、今から三百三十年ほど昔のことである。正保三年(一六四二)、突然、幕府より江戸城に出頭するよう命令が下った。幕府は先代上人・堯秀が引退直前、幕府に断りなく朝廷に願い出て大僧正の位を授かったことに対し、弁明せよというのであった。
堯朝上人としては、まったくあずかり知らぬことであるが、平身平頭先代の軽挙をわび、必死で事情を説明した。しかし、二代将軍・家光の怒りは収まらず、ことはさらにこじれてしまった。上人は二代藩主・藤堂高次にも相談、側面から色々手を尽くしてもらった。
そんな時、家光の側近らが「親鸞聖人の直筆を献上すれば、上様のお怒りもとけよう」ともちかけた。その話を聞き、堯朝上人は家光のねらいは直筆であると感じた。そして、ここで折れれば、幕府の思うつぼである。親鸞聖人の御直筆を手放すことは高田本山にとって滅亡にも等しいーと、この申し出を断った。
最早、なすすべもなく万策尽きた堯朝上人は、その年の八月二十二日、江戸城を下がり、その後、切腹し自らの命を絶った(一説には暗殺されたともいわれる)。まだ三十二歳の若さであった。上人の死は幕府の手前、急病死という形で処理され、記録上にはまったく表れていない。わずかに、その遺骸を葬った東京・浅草の唯念寺に極秘書類として残されていた。しかし、これも関東大震災で焼失してしまった、という。
ひとり残された高松院の嘆きは深かった。それが事故や病死、いや、せめて自らの失策によるものであれば、あきらめもつくが、これではあまりに無念。 高松院は上人の霊を慰めるべく、その七回忌にあたる慶安五年(一六五二)、津の名工・辻越後守重種と氏種に命じて梵鐘を鋳造させた。この鐘にはこんな悲しい話が伝わっている。
結城神社 ~結城宗広

結城宗広が海上で嵐に遇い、この地に打ち上げられたのは延元三年(一三三八)という。そして、ここで彼はその波瀾の生涯を終えた。足利尊氏を討伐できず、無念きわまりない死様であった。「予はここに死ぬが、僧を呼び集めて経を読むな! また、供養もするな! 予の成仏を願うならば、足利尊氏の首を墓前に供えよ!」と言い残して果てたとも伝えられている。
さて、宗広の一族は、藤原秀郷から十一代の孫、朝光が下総国・結城に移り住み、結城氏と名乗るところから始まる。宗広は、この結城氏からさらに分かれた陸奥国白河の結城氏で、白河の関をおさえる白河城主として有力な豪族の一人であった。
元弘の乱(一三三〜一三三三)では護良親王の命旨をうけるや、老体にムチ打ち、新田義貞に味方して鎌倉に攻め入り北条高時軍を殲滅、建武中興に貢献した。彼は後醍醐天皇に志を寄せており、結城氏の惣領として北畠顕家とともに奥州を統治、朝廷に忠勤を励んだ。
しかし、都では、この後醍醐天皇の新政が頓挫、それに乗じて足利尊氏が叛旗をひるがえし、九州より攻め上りつつあった。これを知り、宗広の奥州軍は直ちに京へ上り、楠木正成らと力を合わせ、これを撃破したものの、尊氏は九州で態勢を建て直すや、再度、京に攻め入ってきた。
この戦いで楠木正成は湊川に討死、天皇は吉野に御遷幸という事態の中で、結城宗広と北畠顕家の奥州軍は奮戦するが、顕家は延元三年(一三三八) 五月、和泉堺浦に討死、七月には新田義貞も越前で討死する。このため、宗広は捲土重来を期して北畠親房と義良親王とともに伊勢国・大湊から奥州へと船出した。
だが、天は宗広に味方しなかった。軍船はことごとく遠州灘で暴風雨に遇い、この起死回生策も失敗してしまう。宗広の船はその後、漂流ののちに津の阿漕浦に漂着。そして、この結城神社の地で足利尊氏を恨みながら「残念至極だが、最早これまでじゃ。今一度大湊より出航したいが止むを得ぬ」と言ったあと、刀を逆手に持ち、「予はここに死ぬが.……」の遺言を残し、歯がみをして息絶える。
特集の続きや、津のほんのバックナンバーは弊社にてご覧いただけます。